分子栄養学とは?
最新栄養学のひとつ
分子栄養学は、食べ物の栄養素が身体の中でどのように作用するかを、身体の中の細かい単位(細胞レベル)までみていく栄養学です。どの栄養素が不足するとどういう症状が出るか、なぜ不足しているのか、どう補えばよいかを考え、その人にとっての最適な量の栄養素を用いて、一つ一つの細胞をきちんと機能させていきます。

一般的な栄養学や健康法とどう違うの?
従来の栄養学は、食事摂取基準やバランスの良い食事を重視した「全体的な健康維持」を目的とする考え方です。この考え方では、栄養不足や過剰摂取を控え、主に国民全体の健康向上を目指しています。基準量の栄養素が摂取できているかで「不足」か「過剰」を判断します。
in case of 鉄分不足 アプローチの違い
- 一般的な健康法
- 鉄を多く含む食品(レバーや赤身肉、ほうれん草など)をとる。
- 必要に応じて鉄剤や鉄サプリを使用します。
- 健康診断のHb値で判断されることが多いです
- 分子栄養学的アプローチ
- 鉄が身体の中で吸収されたり、使われる仕組みから、なぜ不足しているのか?を考える。
- 鉄吸収を悪化させる因子(例:胃酸低下や腸内細菌の異常)を特定し、消化吸収を改善するところからアプローチする。
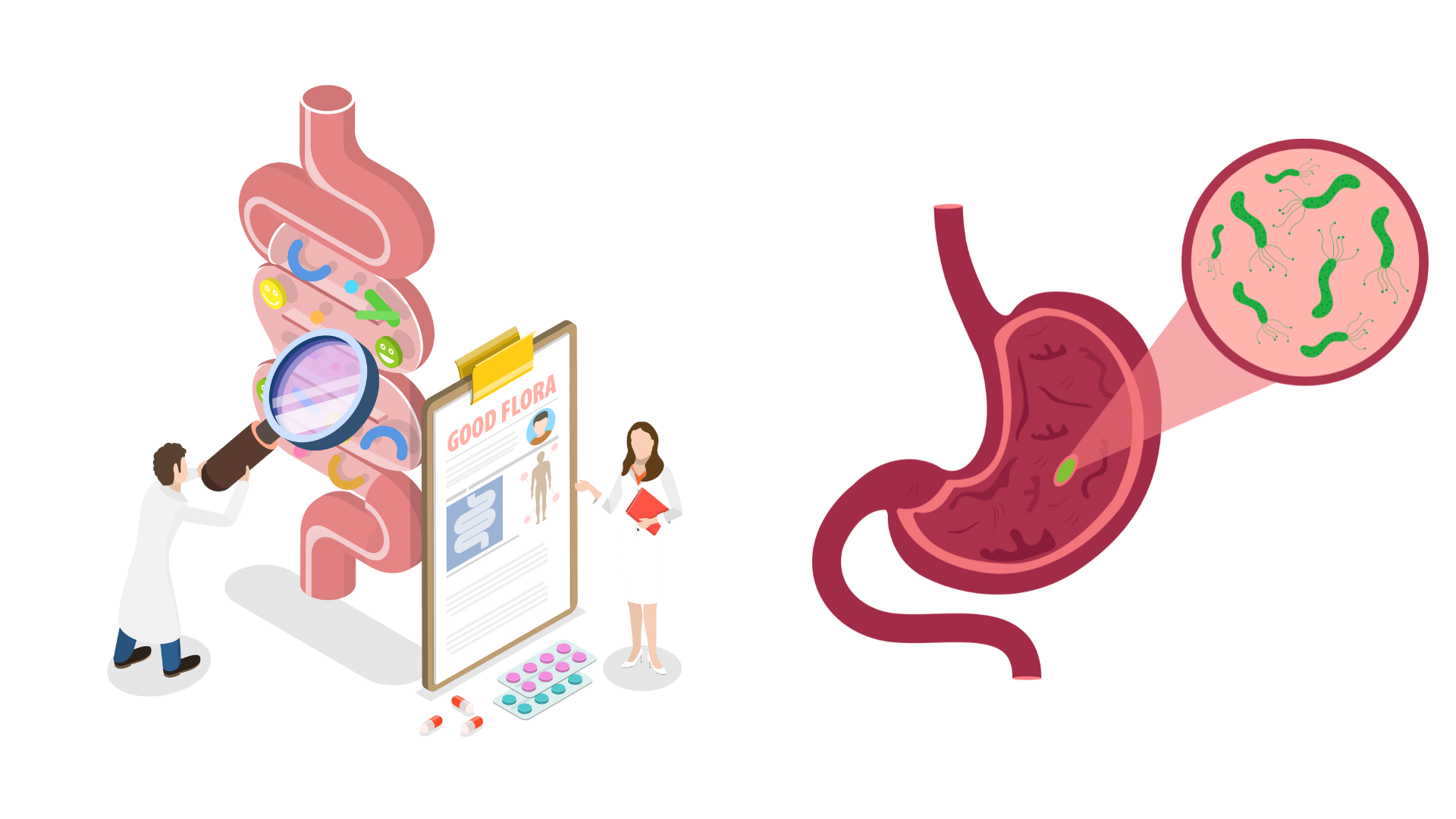
- 鉄だけでなく、たんぱく質やビタミンCなど鉄が作られる仕組みを支える栄養素も同時に補う(むしろ、安易に鉄サプリは補充しない)
- 疲労や頭痛、不安、イライラ、肩こりなど多岐にわたる症状から推察
- 血液検査のHb値は正常でも、潜在的な鉄欠乏を発見できる
in case of 疲労 アプローチの違い
- 一般的な健康法
- 全般的な栄養バランスの改善を提案し、エネルギー補給を重視する
- ビタミンB群などの栄養ドリンク、にんにく注射など
- ストレスの発散、良質な睡眠を心がける
- 分子栄養学的アプローチ
- エネルギー生産の工場(ミトコンドリア)の機能に注目し、エネルギーを作るのをサポートする栄養素(例:ビタミンB群、コエンザイムQ10、カルニチン)を補う
- 慢性炎症(肥満、脂肪肝、慢性鼻炎)など、エネルギーを生産を邪魔しているものが原因の場合、抗酸化物質や抗炎症作用のある食品を導入する
- 腸内環境を調整することで、腸-脳軸の改善を図り、疲労感やメンタル面の回復をサポート
血液データの深読み
健診では正常とされる数値でも、血液検査データの深読み解析を組み合わせることで、個人個人に合わせた対策を考えることができます。(※診断は医師)
根本部分から健康にアプローチできる
薬などの一時的な解決ではなく、なぜその状態が起こっているのか?を突き詰めて、食事と生活習慣によって根本から身体を整えていきます。そうすることで、不調によって隠れていた本来の個性や能力を取り戻すことができます。
まとめ
分子栄養学は、従来の栄養学を補完しながら、個人の特性に応じた「オーダーメイドの栄養アプローチ」を実現する新しい学問です。特定の症状や病態に焦点を当て、科学的根拠に基づいた栄養を介入することで、より精密な健康管理が可能になります。従来の栄養学とともに活用することで、健康維持と病気予防の新しい可能性が広がるでしょう。

